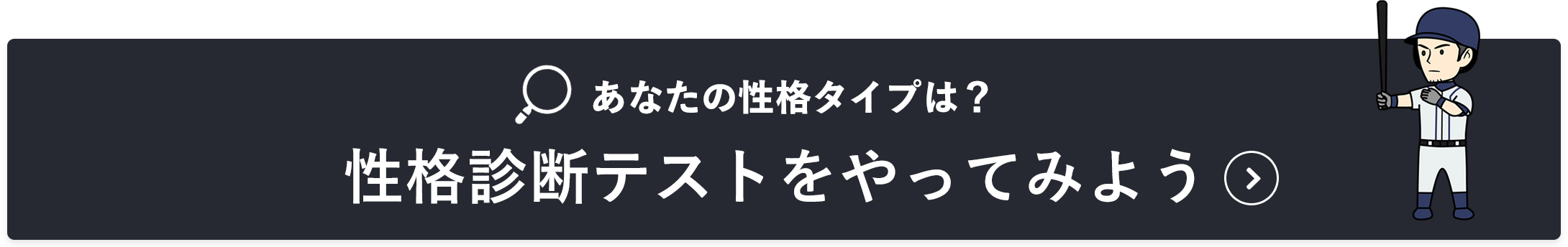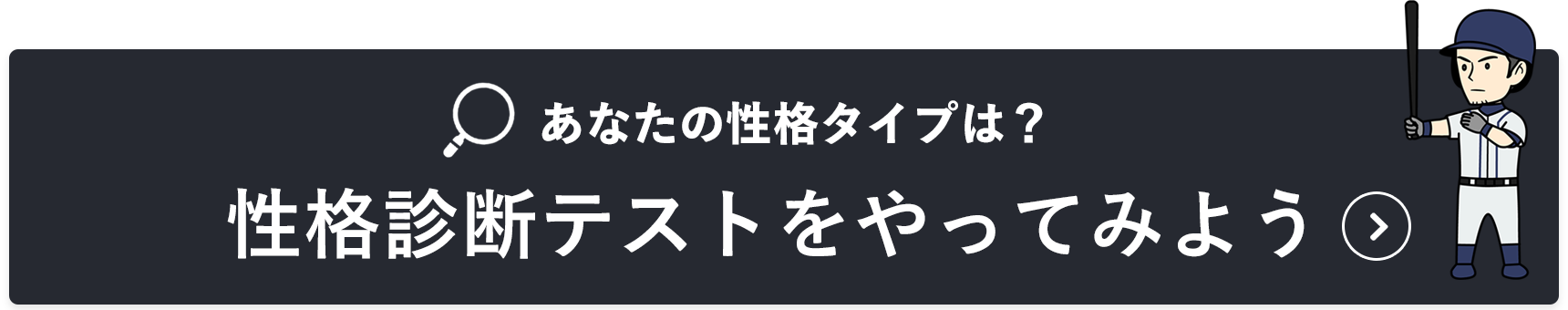4あなた独自の強みと今現在の仕事との関係性
強みというよりただの性格・特徴ですが、知的好奇心と人への関心が強く、比較的多様な人と人間関係を築くことができるタイプです。
知的好奇心の強さはVC(に限らないかもしれませんが)の仕事の大前提です。例えば、不動産業界や保険業界の投資先と戦略の議論をした直後に、初対面の起業家とマンガ・アニメや観光の話をするなど、日々触れる分野が多岐に渡ります。もちろんAIやブロックチェーンなど新しい技術・トピックを取り扱うことも多いです。自分の関心分野や専門分野が定まってくると一定絞られますが、それでも日々新しい知識との出会いが多く、その度調べたいことや考えたいことがたくさん出てきて刺激を受けます。
人への関心は投資検討や経営支援の文脈で重宝します。持たざる者であるスタートアップの一番の資産は人です。どんな起業家やどんな経営チーム、メンバーが集まっているかでその後の成長が大きく変わります。私は投資検討の中で基本的に経営陣とはそれぞれ1on1の時間をいただき、メンバーも数名お話しさせてもらいますが、人に関心が強いゆえにこの時間を通じて会社を構成する個を知り、会社を立体的に理解していくプロセスが好きです。経営支援においても、マーケティングや営業など各分野のエキスパートと日頃から繋がりを作っていることで自分の専門外の領域についても間接的に支援ができるので、ネットワーク・人脈の広さや深さが重要ですが、ここも厭わないのは人が好きだからだと思います。
上記と少し被りますが、多様な人と人間関係を築けることは転勤族だった幼少期から定期的に、ある種強制的に全く新しいコミュニティに溶け込むことを求められていたことで身に着けた特性な気がしています。実はこれがVCとしての動き方にも活きてると今になって感じています。
現職の上司でもあり日本ベンチャーキャピタル協会元会長の仮屋薗さんが作ったVCの行動規範「ベンチャーキャピタリスト12訓」の第1訓にも以下のようにあり、自分が人材のハブになることが第一歩であり、いい人と繋がりいい人を繋げることで付加価値を生んでいく類の仕事であり、自分の性格が活きる部分だと考えています。
優秀な人材のいる場所、時間、きっかけを探せ。
そこに何度でも通って、一人一人と、仕事ではなく、しっかりと友人になれ。
やがて自分自身が、人材の集まる場となる。

5仕事をしている中で、心が大きく動いた瞬間
投資を通じで会社の組織が成長していく様はいつも心が動きます。
スタートアップ投資の場合は資金使途の多くが人材採用なので当たり前ではあるのですが、例えば10人しかいなかった会社が50人100人と増えていき、普段は経営陣としかコミュニケーションをしないので久々に全社会に参加するとメンバーの方々に「誰だろう?」という目をされて段々と外様感を感じていくことが、寂しいようでとても嬉しい瞬間だったりします。
自分が投資をする際に信じた未来に向けて着実に成長し、共感した多くの人の想いを乗せてさらに加速していく様子が好きなのだと思います。
デレク・シヴァーズの「社会運動の起こし方」というTEDトークがあります。1人のバカをリーダに変え社会運動に発展させるのは最初のフォロワーの存在だ、ということを示す3分間の動画で、私も好きな動画の1つです。
起業家や経営陣数名しかいないフェーズの会社にも投資を実行しますが、VCはある種最初の外部からのフォロワー、お墨付きを与える役割だったりもします。幸いファンドの過去の投資実績から、「あのVCが投資しているのであればこの会社は伸びるのでは?」というシグナリング効果が一定あるので、よりお金が集まりやすくなったり、いい人が紹介してもらいやすくなったりします。
もちろんその分1つ1つの投資の責任は重く、社内の投資委員会を通すハードルも高いのですが、反対に投資をした時の会社成長の加速はやはりVCの醍醐味の1つだなと思います。
ちなみに、私はまだVCとしての経験値も浅く歴も短いのでこれからですが、一緒に挑戦してきた起業家や経営陣が時の経過と共にスタートアップエコシステムの中でのキーパーソンになっていき、将来的に自分の仲間たちで実現できることが増え仕事の幅が広がっていくという絵を想像することが、個人的には強いモチベーションになっています。
これも同じく「ベンチャーキャピタリスト12訓」の第12訓に示されていて、何度も読み返しています。
時を経て、一旦の成功を為し得た時、かつての夢見る若き起業家は、先進の経営者に、新卒だった若者は頼もしいマネージャーとなっていることに、あなたは気付き、そして共に喜びを分かちあうだろう。
その永かった道程に、あなたは真の報酬を見出だす。
6公認会計士という仕事に関連して深く悩んだこと、それをどのように乗り越えたか
既にVCの方が期間が長くなっているので題目を「公認会計士」よりは「VC」と捉えて、また具体的なエピソードではなく恐縮ですが、今の仕事は日々悩みや反省の連続です。
投資テーマだけでなく日々の時間の使い方も完全に自由で正解が存在しない仕事だからこそ、雲を掴むような感覚で自分なりにテーマ探索や習慣作りに取り組んでいたり、投資判断や経営判断も情報が不十分だったり市場変化が読み切れなかったり、不確実性が常にある中で意思決定をするので悩みます。
また、スタートアップはもちろん全社が成功するわけではなく、縮小や撤退の意思決定が必要な時も往々にしてやって来るので、起業家や経営陣に対して伝えにくいことを伝えなくてはいけない時、どんな場でどんな話の組み立ての中でどんなニュアンスで伝えるべきか、いつもケースバイケースで悩みます。
反省も、もっとこういう風にコミュニケーションを取れば良かった、この意思決定・経営判断は遡ったら同じことをしないな、など、悩みと同様に人や判断に対してのことが多いです。
会社経営に関わる仕事だからこそかつ起業家や経営陣は人生を賭けて会社のミッションに挑んでいるからこそ、皆とてつもないエネルギー量で仕事していて、それゆえに悩むことも反省することも多いのだろうと理解しています。
ただそれも全て学びで、シリコンバレーの著名なアクセラレーターY Combinatorが言うように「スタートアップの平均的な結果は死」と認識した上で、もちろんそれぞれの起業や投資で成功のために全力を尽くすのですが、長い時間軸で日本社会に意味のある大きな成功を1つでも多く共に作れたらいいな、たとえ今の挑戦がうまくいかなくても次に繋がるようにもがけるだけもがこう、と思うようにしてます。

 革命家タイプ
革命家タイプ