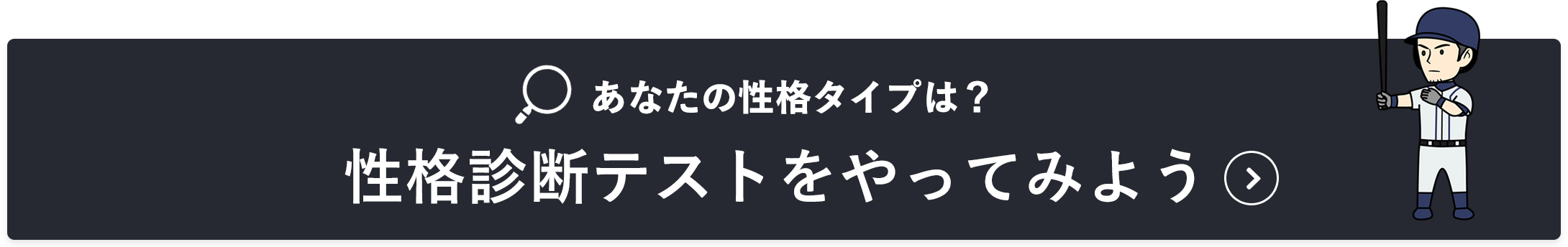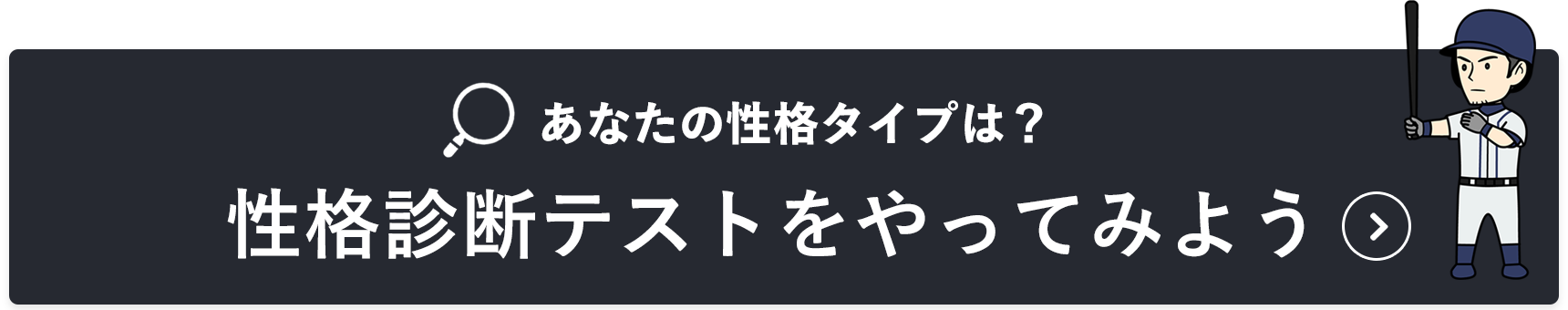佐々木博章公認会計士事務所
所長
佐々木 博章 ささき ひろあき

100%のパフォーマンスができなくなれば、自らバットを置くべき
 革命家タイプ
革命家タイプ

京都府出身
同志社大学商学部 卒業