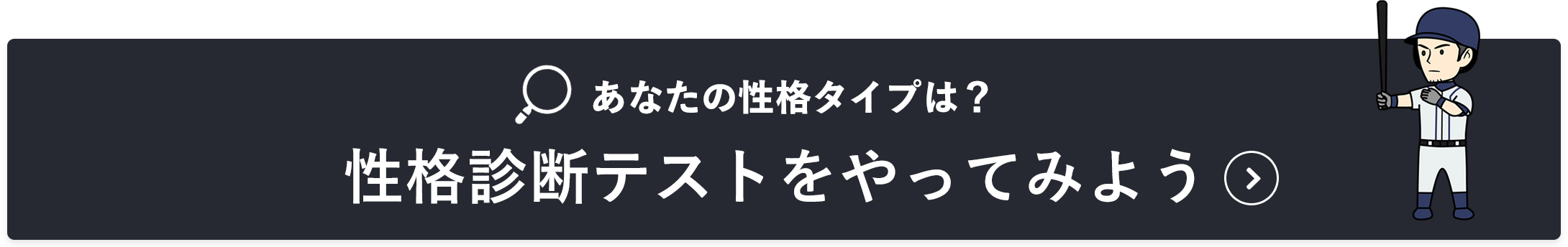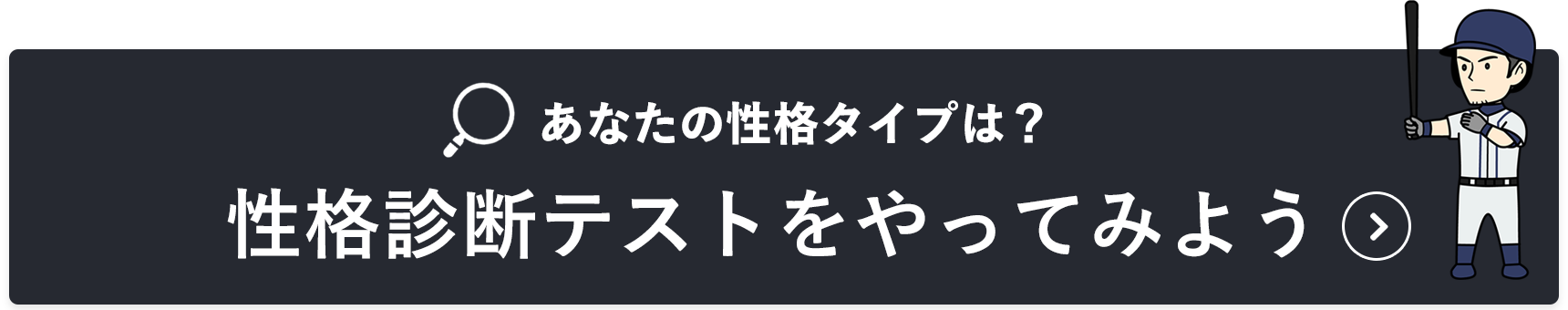2監査法人における経験およびその後のキャリア選択のきっかけ
友人が「貴女の行動にはいつも驚かされる」と言う。心当たりがある。人生の選択に悩んだ時に、ハードな選択肢を選ぶ悪い癖があると。
1) 監査法人で会計監査、研修講師等を経て、「変化の先へ」
銀行・信用金庫、メーカー、不動産を中心に監査に従事した。当時の上司の口癖「あの会計士は付加価値を提供した、と言われるような改善提案をせよ。」を胸に、問題の指摘だけではなく改善提案まで沢山した。
法人内で研修講師をした縁で、研修部に誘われ異動。多くの研修を自分で企画し、講師をした。教えるのが好きだった。難関は提携先の2週間の研修。英文教材は段ボール2箱。1年かけて和製化し、実行しマネジャーに昇格。時は、会計ビッグバン、品質管理の部門に誘われて異動するが、SOX法成立の契機となった企業会計スキャンダル群により、提携先が解散。
会計もSOXも、日本は米国の後追いだ。「変化の先」に行けば、いつか追いつけるのではないか。損保の経験も知識もないのに、米系への転身に踏み切った。
2) 米系損保でボードに参加、米国基準・管理会計・PMIに奮闘
AIGでは予算・四半期見込の提出先がRegionで英語に苦労した。買収資金をNYから調達し、撤退先に頻繁に通いPMI。リスク管理委員長を拝命し、ボード、人事委員会にも参加した。システムで米国基準/日本/税務と3つの帳簿体系を持つ仕組みや勘定科目等のコーディング、移転価格を考慮した業績評価の仕組み、月次予算データベース、マトリックス組織の各機能の報告パッケージ、決算早期化・USSOXなど、基礎は一通りAIGで学んだ。
PMIが落ち着いた2005年頃、保険毎日新聞に「IFRS」関連が連載されていた。子会社の会計は本社の指示で動く。「IFRSが来る。会計と商法が変わる。子会社ではなく本社で、自分が指示を出したい。」
3) 日系アパレル企業本社で連結・単体のシステム導入に奮闘
内定頂いた数社のうち、連結チームを立ち上げるという FR を選んだ。当初はエクセルでの連結だったが、連結・単体にERPを導入するプロジェクトがあり、担当する子会社2社のERPを入れ、連単の連動がよくわかった。
Accounts Payable/Receivableの機能等、外資時代の業務も役立ち、組織や業務の時間軸・空間軸で立体的に見えるようになった。連結パッケージも作り直した。メンバーに恵まれ仕事は楽しかったし、今も交流する。が、当時、娘は10歳。祝日が通常出勤で、後ろ髪を引かれる思いがした。
半年経ち、転職したことを知らないエージェントから連絡が入る「H社で新たに連結グループを作る。リーダー募集」。FR社は子会社20社の連結決算に45日かかるのに、68社もの子会社を2週間で連結して発表している。売上が同規模、営業利益は同水準なのに、残る最終利益が大きい。どうしたらそんなことができるのか。この興味で転進を決めた。
FRで年度末決算を終え、退職前の最終引継ぎをしていた12月下旬、転身先が経営統合を発表する。採用面接でそんな話はない(会社からすれば言えるはずもない)…。転進先で待っているのは激務…。これも運命、と直進する。
4) 日系光学機器メーカー本社へ。入社早々に経営統合、重要ミッションに奮闘
激務を覚悟して入社したが、予想以上だった。立ち上げたばかりの連結のリーダーになり、経営統合、IFRS導入、連結決算体制構築と JSOXの4つのミッションに奮闘することに。
入社数日で統合準備委員会に参加、株式交換比率を検証するため、自社もDDを受ける。事業部長や担当者の名前や顔、誰にコンタクトすべきかも解らない時期の、いきなりのDD対応で、事業や組織を短期総なめできた。これは幸運で、のちの事業部方針等の策定に大いに役立った。
米欧亜の3地域を訪問し、自社のSBUの考え方やパッケージを説明した。複雑な合併統合と組織の解体は、先方にとっても当方にとっても相当の負荷だった。それと並行してのIFRSは重く、半年も働いていないのに10年分働いたような濃厚な年月だった。
当時、IFRS連結財務諸表は日本の制度で認められていない時代。誰も受け取らない決算書でも、日本も含めてグローバルにIFRSに統一して決算する、という。経営統合があってもその優先順位は高いのだ、と。昼間は統合準備で時間がとれない。早朝と夕方以降、土日祝日がIFRSに充てられる時間だった。
IFRS以上に統合と連結決算体制整備が大変だった。入社後9か月で子会社の数は100社を超えた。連結メンバーが合併処理の後、戦線離脱して採用活動の日々。監査人も変更、IFRS期首監査も振り出しに。
1年ほど経過し、採用と監査人交代が落ち着いてきた頃、日本でIFRS任意適用の話が出始めた。着手が早かったH社は、日本で2番目、初度適用からのIFRS移行は実質1番目になった。グループの実績をIFRSという同じ物差しで測る、という当時のCFOのビジョンや先見の明に感服する。偶然、自分も「乗り遅れた変化に追いつきたい。日系本社で指示を出したい」という想いがあった。だからこそ、大変ななか4-5年IFRSに取り組めたのだと思う。
任意適用2年後の2013年に有価証券報告書も株主総会の3週間前に提出し、以来、同部で継続中である。
5) 50歳直前に大学院へ。社会人と学生の二足の草鞋生活に奮闘
IFRS導入後、問い合わせや講演依頼が殺到する。全部に対応できない。代わりに『週刊経営財務』に『IFRSを導入したわが社の取り組み』をCFOのチェックを経て匿名で掲載した。匿名?会社の顔は社長。CFOすら顔出ししていないのに、一社員が名前や顔を出す訳にはいかない。
取材も基本お断り、知り合いの依頼のみ数件受けた。その中に、大学院のゲスト講師があった。教授は監査法人、事業会社CFOを経た会計士だった。どうしたら教授のようになれるのか質問したところ、「論文の心得が必要。夜間でもよいから修士、できれば博士をとれ」と助言を受け、大学院を探し始めた。働きながら夜間で修士号をとれるのはビジネススクールだった。
ベテランのCFOと部長が退き、新体制下で部長になった。管掌範囲にERPや内部統制が増え、新たに経営基盤強化プロジェクトも拝命する。10以上ある事業部のKPIや予実を財管一致で一望できる仕組みの構築。KPIや予実管理の仕組みは事業部毎に異なる。事業部ごとにヒアリング、時間がかかる。その間もM&A案件やトラブル、決算があり、進まない。
自分のグランドビジョンがないからだ、一旦頭を冷やしたい、と退職を願い出て、事業部への異動を打診された。異動先から近い夜間学校なら通えるかも知れない…。願書締切間際に2日で研究計画書を書き、論文試験を受けた。計画書のテーマは管理会計だったが、1 年間授業を受けた中で最もハードな課題を出した先生に師事するのが一番成長しそうな気がした。戦略ゼミだった。修士号や博士号を取りやすい会計を選ぶべきで、戦略は素人。自分の悪い癖(成長できそうだと思うハードな選択肢を選ぶ)が出てしまう。博士に進めなくても今、この先生から学びたい…。
本社から異動し、各国や地域のCFOを支援しながら内部監査と子会社の監査役を担当した。数年前に買収した子会社は赤字続き、CEOからも直接メールが入る。「ビジネスの重病人。どうしたら健康体になれるかという視点で監査せよ」。大学院の研究テーマに設定し、子会社社長の了解も取り、データを直接入手。製品・顧客・活動別に仮説を検証し、仕事と研究の区別なく取り組んだ。なお、極秘情報を含む研究論文は非公開だ。
6)大学院を修了後、ベンチャーに転身
2020年3月に卒業、翌4月に博士を勧めてくれた教授から 3 年ぶりの電話があり、監査役の会社を紹介された。これまでにIFRSパネル登壇は3回だけ、依頼が殺到してから受けたのは 1 回だけ、偶然そこでパネルをご一緒した会社だった。縁を感じた。程なくもう1社非常勤が決まった。
ビジネススクール修了後、起業する学友が多い。自分は起業まではできないが、小さな会社の常勤監査役なら経営も傍で見られるし、監査役をやるなら初めに徹底的にやる方が覚えられる。「2社の非常勤役員をしながらの常勤は無理」と書類選考で落とされることが多かったが、ベンチャーが常勤として受け入れてくれた。常勤をやるなら今しかない…。
上場している非常勤先を参考にしながら、監査役監査体制をゼロから作った。コロナ禍で出社しなくても社内の会議録や会話、会計帳簿、決裁資料はツールでほぼ全て見ることができ、監査はやりやすかった。証券審査では、当初「非常勤2社を兼務する監査役の常勤性」を問題視されたが、週5(2時間の日もある)の活動を調書に残し、黙らせた。内部監査も一巡するまで伴走し、自走できるようにした。
意思決定やアクションの速さ等、大企業にない発見も多かった。監査調書体系と手法は、非常勤先にも勧めている。

 冒険家タイプ
冒険家タイプ